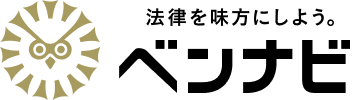広告|この記事は株式会社アシロの提供です。
「弁護士事務所のホームページをどのように制作すればよいのかよくわからない」
「ホームページ制作にはどの程度の費用がかかるのか把握しておきたい」
ホームページは、自社の認知度向上や集客を図るうえで欠かせないツールです。
しかし、ホームページ制作の知識がなく、なにから手をつけてよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、弁護士・法律事務所がホームページを制作する際の流れや、制作会社に依頼した場合の費用相場などを解説します。
おすすめのホームページ制作会社なども紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事でおさえたい5つのポイント
目次
- 1 弁護士・法律事務所がホームページを制作する目的とは?
- 2 弁護士ホームページのSEO対策の基本
- 3 検索順位を上げるコンテンツ制作のコツ
- 4 弁護士ホームページの掲載必須コンテンツ一覧
- 5 弁護士ホームページのデザイン形式を比較
- 6 弁護士ホームページの制作費用相場
- 7 制作を依頼する場合と自作する場合の比較
- 8 ホームページ制作に使える補助金・助成金
- 9 【制作費用を徹底比較】弁護士・法律事務所向けホームページ制作会社10社
- 10 【制作事例】株式会社アシロが手掛けた、弁護士・法律事務所ホームページ
- 11 よくある質問(FAQ)
- 12 まとめ|成果の出る弁護士ホームページを作るには
弁護士・法律事務所がホームページを制作する目的とは?
弁護士がホームページを制作する目的は一つではありません。
集客、信頼構築、ブランディング、情報提供など、複数の役割を同時に担う重要なツールとして機能します。
あらかじめ目的を整理しておくことで、「何を重視したホームページにするのか」「どのような構成・設計が必要か」が明確になり、制作後のミスマッチを防ぐことにもつながります。
ここでは、弁護士がホームページを制作する代表的な4つの目的について解説します。
法律相談の集客を増やすため
弁護士がホームページを制作する最大の目的は、法律相談の集客を安定的に増やすことにあります。
近年、弁護士を探す際の行動は大きく変化しており、知人紹介や電話帳ではなく、インターネット検索を起点とするケースが主流です。
実際に、弁護士に相談した経験がある人のうち、半数以上が「インターネット検索で弁護士を探した」と回答しています。
【参考】株式会社レントラックス「弁護士選びに関する意識調査」(調査期間:2024 年 8 月 28–29 日、公開日:2024 年 9 月 17 日)
そのため、特に独立・開業された弁護士は、まずホームページの作成を考える方が多いようです。
また、ホームページ上では
- 取扱分野
- 相談の流れ
- 費用の目安
- 弁護士の考え方や人柄
といった情報を分かりやすく整理して掲載することで、相談者は安心して問い合わせを行えるようになります。
ホームページは24時間365日稼働する営業窓口として機能します。
オンライン相談予約フォームや問い合わせフォームを設置することで、営業時間外でも相談の取りこぼしを防ぎ、機会損失の軽減を目指していきましょう。
【参考】弁護士が独立開業するための完全ガイド|流れやメリット、ホームページ集客などを徹底解説
地域に特化した顧客を獲得するため
法律事務所にとって、特定地域での認知度向上は極めて重要です。
多くの相談者は、
「地域名+弁護士」
「地域名+法律相談」
といったキーワードで検索し、通いやすく、身近に感じられる事務所を探しています。
そのため、ホームページで地域名を意識したSEO対策を行うことで、特定エリアに住む潜在的な相談者へ効率よくアプローチすることが可能になります。
さらに、Googleビジネスプロフィールと連携することで、Googleマップ上での表示回数やクリック率が向上し、地域検索からの流入も見込めます。
例えば、東京都世田谷区に事務所がある場合には、
「世田谷区 弁護士 相続」
「二子玉川 法律相談」
といった具体的な検索ニーズを想定したページ構成を行うことで、地域密着型の集客が実現しやすくなります。
信頼性・ブランディングの向上
法律相談は、人生や財産、家族関係に直結するデリケートな問題が多く、「この弁護士に任せて大丈夫か」という信頼感が依頼の決め手になります。
ホームページは、相談者が初めて弁護士と接点を持つ場であり、第一印象を左右する重要な要素です。
- 弁護士や事務所の雰囲気
- 考え方や価値観
- 対応スタンス
といった情報を丁寧に伝えることで、相談者は心理的な安心感を得ることができます。
さらに、解決事例や実績、相談者の声などを掲載することで、「実際に問題を解決してきた事務所である」という裏付けが生まれ、信頼性の向上につながります。
強みや専門分野をアピールする
ホームページは、事務所の強みや注力分野を明確に伝えるための最適な媒体です。
弁護士事務所は数多く存在するため、
「どの分野に強みがあるのか」
「どのような相談に向いている事務所なのか」
が伝わらなければ、比較検討の段階で選ばれにくくなってしまいます。
取扱分野ごとにページを分け、
- 対応内容の具体例
- これまでの対応実績
- 依頼者への向き合い方
などを丁寧に説明することで、相談者は「自分の悩みに合った事務所かどうか」を判断しやすくなります。
なお、アピールの際には、弁護士法および日弁連の広告規程を遵守し、誇張表現や誤解を招く表現を避けることが重要です。
弁護士ホームページのSEO対策の基本
弁護士のホームページ制作において、SEO(検索エンジン最適化)対策は欠かせない要素です。
検索結果で上位に表示されることで、広告に頼らずとも継続的な集客が期待でき、長期的な経営安定にもつながります。
ここでは、弁護士業界におけるSEO対策の基本的な考え方を解説します。
弁護士業界における検索ニーズの傾向
弁護士を探すユーザーは、多くの場合、具体的かつ切迫した悩みを抱えています。
そのため、「〇〇トラブル 弁護士」「〇〇(地域名) 法律相談」といった具体的なキーワードで検索する傾向があります。
また、法律サービスは費用も高額になりやすいため、ユーザーは複数の事務所を比較検討します。
したがって、単に上位表示されるだけでなく、検索結果での差別化要素(料金、実績、専門性など)を明確に示すことが重要です。
ローカルSEO(MEO)で地域名+弁護士を狙う
弁護士業界では地域密着型の集客が極めて重要であり、ローカルSEO(MEO:Map Engine Optimization)対策は必須の施策となります。
「地域名+弁護士」や「地域名+法律相談」といったキーワードで検索された際に上位表示されるよう対策しましょう。
具体的には、Googleマイビジネスの登録と最適化が必須です。
正確な事務所情報(住所、電話番号、営業時間)を登録し、写真の追加、最新情報の投稿、顧客からの口コミへの返信を積極的に行うことで、検索結果やGoogleマップでの露出を高めることができます。
専門分野別のキーワード設計例(例:離婚・相続・交通事故など)
集客したい専門分野に応じて、ターゲットとするキーワードを具体的に設計することが重要です。
例えば、以下のようなキーワードが考えられます。
- 離婚問題: 「離婚 弁護士 費用」「離婚 調停 弁護士」「熟年離婚 相談」「不倫慰謝料 請求」
- 相続問題: 「遺産分割 弁護士」「遺言書 作成 費用」「相続放棄 相談」「遺留分 侵害額請求」
- 交通事故: 「交通事故 弁護士 費用」「後遺症 慰謝料」「人身事故 相談」「示談交渉 弁護士」
これらのキーワードをホームページのタイトル、見出し、本文oogleビジネスプロなどに適切に盛り込むことで、関連性の高い検索からの流入を増やすことができます。
GoogleのE-E-A-T対策(専門性・経験・権威性・信頼性)
Googleの検索アルゴリズムでは、コンテンツの品質を評価する上で「E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)」が非常に重視されています。
【参考】Google検索セントラル
特に法律分野は「YMYL(Your Money Your Life)」と呼ばれる、人々の人生や金銭に大きな影響を与える領域に該当するため、E-E-A-T対策がより一層重要になります。
- 専門性 (Expertise): 法律の専門家として深い知識や見識があることを示す。
- 経験 (Experience): 実際にその分野での経験や実績が豊富であることを示す。
- 権威性 (Authoritativeness): その分野におけるリーダーや情報源として認められているか。
- 信頼性 (Trustworthiness): 正確で信頼できる情報を提供しているか、安全なサイト運営をしているか。
具体的には、弁護士の詳細なプロフィールや解決事例、専門分野に関するコラム記事、メディア掲載実績などを充実させましょう。
これらの要素をホームページ全体で示すことで、Googleからの評価を高め、検索順位の向上につながります。
検索順位を上げるコンテンツ制作のコツ
弁護士ホームページの検索順位を向上させるためには、単に情報を羅列するだけでなく相談者にとって価値のある質の高いコンテンツを継続的に提供することが不可欠です。
ここでは、検索エンジンから高く評価されるコンテンツ制作のコツを解説します。
解決事例・実績を活用したページ構成
法律相談を検討しているユーザーにとって、最も関心が高い情報の一つが「解決事例」や「実績」です。
自身の抱えるトラブルが解決可能であるか、そしてその事務所が実際に問題を解決できる能力があるかを判断する重要な材料となります。
そのため、解決事例は単に羅列するのではなく、以下の効果的な構成要素を含めましょう。
- 事案の概要:年代、性別、問題の背景を簡潔に説明
- 争点と課題:法的な論点や解決の難しさを明示
- 弁護士の対応策:具体的なアプローチや戦略を詳述
- 解決結果:数値や期間を含む具体的な成果
可能であれば、匿名化した上で顧客の声や感謝の言葉も掲載することで、信頼性が一層高まります。
よくある質問(FAQ)のSEO活用法
「よくある質問(FAQ)」は、ユーザーの疑問を解消するだけでなく、SEO対策としても非常に有効なコンテンツです。
相談者は「費用」「期間」「流れ」「家族や職場にバレるか」「相手方対応」など、具体的な不安をそのまま検索します。検索で入力される質問を先回りして丁寧に回答できると、流入が増えやすくなります。
FAQ作成のコツは、次の2点です。
- 実際に相談で聞かれる質問を起点にする(現場の言葉をそのまま使う)
- 回答は、“結論→理由→補足→次の行動”の順で簡潔にする
さらに、FAQから「詳しい解説ページ」へ自然に誘導できると、読者は次のトピックを読みたくなり、滞在時間も増えます。
コラム・ブログの書き方と投稿頻度
コラムやブログは、ホームページの専門性や情報量を高め、継続的な集客につなげる重要な要素です。
法律用語の解説だけでなく、相談者が迷いやすいポイント(証拠、相手対応、費用の考え方、期限、手続きの流れ)を具体的に扱うと読まれやすくなります。
執筆時のポイントは、次の通りです。
- 専門用語は噛み砕き、例を入れる(「つまりどういうこと?」を先回り)
- 1記事で全部を説明しない(関連トピックへ内部リンクでつなぐ)
- 結論だけで終えず、「次に何をすべきか」を示す
- 法改正や運用変更があり得る箇所は、更新前提で書く
投稿頻度については、無理のない継続が最優先です。
「月1回でも良いので、相談者の疑問に刺さる高品質記事」を積み上げるほうが、薄い記事を量産するより成果につながりやすい傾向があります。
また、季節性のあるテーマ(年末年始の相続、新年度の労働問題、長期休暇中の交通事故など)を意識してコンテンツ計画を立てると、検索需要の波に合わせた集客ができます。
専門家プロフィールの最適化
検索エンジンは、記事の執筆者情報も重視します。法律分野のようなYMYL領域では、特に「誰が書いたのか」「どんな経験に基づくのか」が信頼性に直結します。
プロフィールに盛り込みたい要素は以下の通りです。
- 顔写真
- 詳細な経歴(出身大学、司法試験合格年、実務経験年数など)
- 取扱分野・注力分野(具体的に)
- 所属団体・委員会・資格
- 執筆・講演実績
- 相談者へのメッセージ(価値観・姿勢が伝わる言葉)
「立派に見せる」より、「相談者が安心して相談できる材料を揃える」ことを意識すると、結果的にSEOにも強いサイトを目指せます。
弁護士ホームページの掲載必須コンテンツ一覧
次に、法律事務所のホームページに掲載すべき必須コンテンツを紹介します。
掲載内容はホームページの質を大きく左右するため、最低限の情報は漏れなく明記しておくことが重要です。
事務所概要とアクセス情報
法律事務所のホームページには、事務所概要を掲載する必要があります。事務所概要とは、簡単に言うと「事務所のプロフィール」です。具体的には、以下のような情報をまとめたページを作成しておくとよいでしょう。
- 事務所名
- 設立年月日
- 所在地
- 連絡先(電話番号/FAX番号)
- アクセス情報(最寄駅・地図・駐車場
- 代表者名
- 所属弁護士数
このほか、代表者の挨拶や事務所としてのポリシーを掲載すると、相談者が雰囲気をつかみやすくなります。
特にアクセス情報は、Googleマップ埋め込みだけでなく「出口からの道順」「ビルの目印」「受付方法」まで書くと、来所ハードルがより下がるでしょう。
弁護士紹介(写真・経歴・対応分野)
ホームページの掲載内容には、弁護士の紹介も欠かせません。依頼先を探している顧客に、信頼できる弁護士が在籍していることをアピールする必要があります。
掲載したい情報例は以下の通りです。
- 氏名・顔写真
- 挨拶(弁護士としてのポリシー)
- 経歴
- 所属
- 対応分野
- 著書・論文・講演
- 相談者からよく聞かれる質問への回答(人柄が伝わる)
多くの法律事務所では、弁護士一人ひとりのプロフィールページを用意しています。相談者は“相性”も重視するため、業務への向き合い方や説明の姿勢が伝わる文章があると効果的です。
取扱業務と料金表
法律事務所がどのような業務に対応しているのか、そして費用がいくらかかるのかは、相談者の意思決定に直結します。
取扱業務・分野について
単に「対応可能」と記載するだけでなく、
- どのような相談が多いか
- どんな手続きに強いか
- 対応体制(複数名体制、オンライン対応など)
を具体的に説明しましょう。
また、相談者は「自分のケースも相談していいのか」を気にします。よくある相談例を箇条書きで載せるだけでも、問い合わせの心理的ハードルは下がります。
料金表
料金表は相談者の最大の関心事であり、透明性が信頼獲得の鍵となります。
着手金、報酬金、実費、追加費用が発生する可能性などを分かりやすく整理し、無料相談の有無や特記事項(分割可否、見積もりの考え方など)も明記しましょう。
「安さ」ではなく「納得感」を作ることが重要です。料金が明確だと、相談者は比較検討しやすくなり、結果的に問い合わせも増えやすくなります(レントラックス調査でも、サイトで重視する情報として「取扱分野の詳細」「料金体系」が同率1位という結果が示されています)。
参考:【弁護士選びのリアル】過去5年以内に弁護士に相談した人の54.0%が、弁護士探しに「インターネット」を利用 6割以上が、弁護士の「SNS発信」を重視
実績・解決事例・クライアントの声
実績・解決事例は、弁護士の実力を証明する最も説得力のあるコンテンツです。
プライバシーに配慮しながらも、可能な限り詳細な事例を掲載することで、ユーザーは自身の問題解決のイメージを具体的に描けるようになります。
クライアントの声は第三者からの評価として高い信頼性を持ちます。
その一方で、内容が薄いと効果が出にくい側面もあります。単なる感謝の言葉だけでなく、具体的にどのような点で満足したか、弁護士の対応で印象的だった点などを詳しく掲載することで、相談者の不安解消につながります。
お問い合わせフォーム・予約導線
ホームページを訪れたユーザーが、スムーズに弁護士へ連絡できる導線は必須です。
入力項目は必要最小限に絞り(相談希望日時、相談内容、氏名、連絡先など)、スマホで入力しやすいフォーム設計にしましょう。
さらに、フォーム送信後の自動返信メールに、
- 今後の流れ
- 返信目安
- 初回相談で準備すると良いもの
などを記載すると、相談者の不安が減り、キャンセル率も下がりやすくなります。
弁護士ホームページのデザイン形式を比較
ホームページのデザインの種類として、主に「シングルページ」と「複数ページ」があります。
加えて現代では「スマホ対応(レスポンシブデザイン)」が必須です。
シングルページの特徴とメリット
シングルページとは、1枚の長いページに情報を集約した形式です。スクロールだけで、事務所概要から取扱業務、料金、お問い合わせまで順に読めます。
メリットは、ユーザーが迷いにくく、重要情報に触れやすい点です。制作期間が短く済み、費用を抑えやすい傾向もあります。
特に「まずは名刺代わりに整える」「開業直後で情報が少ない」場合は相性が良いです。
一方で、掲載できる情報量に限界があり、コラムやFAQなどSEO向けのコンテンツを増やしにくい点が課題になります。
将来的にSEOを強化したいなら、最初から拡張できる設計にするか、段階的に複数ページ化する前提で作ると安全です。
複数ページ構成のメリットと運用性
複数ページとは、目的ごとにページを分ける形式のことです。
たとえば、事務所概要・取扱業務・弁護士紹介・お知らせ・問い合わせなどを紹介するページが、それぞれ独立している状態をイメージするとよいでしょう。
なかには各ページをさらに細分化し、ホームページが階層構造になっているケースもあります。
複数ページでホームページを制作するメリットは、多くの情報を伝えられる点です。
シングルページには収めきれないほどの情報量でも、目的ごとにページを分ければすっきりと整理することができます。
また、複数ページを閲覧しようとすると自然とホームページ内での滞在時間が長くなり、検索エンジンに有用なサイトだと判断されやすくなることも覚えておきましょう。
ただし、シングルページでホームページを作成する場合に比べ、外注費用が大幅に高くなる可能性がある点は注意が必要です。
スマホ対応(レスポンシブ)とアクセシビリティ
多くのユーザーがスマートフォンやタブレットからインターネットにアクセスするため、これらのデバイスで快適に閲覧できる設計は必要不可欠です。
レスポンシブデザインでは、画面サイズに応じて自動的にレイアウトが最適化され、どのデバイスからでも快適に閲覧が可能になります。
アクセシビリティの重要な要素
- フォントサイズ:モバイルでも読みやすい16px以上
- タップ領域:44px以上のボタンサイズ
- 読み込み速度:3秒以内を目標
- ナビゲーション:シンプルで分かりやすいメニュー
また、高齢者や視覚に障害のある方も相談者になり得るため、文字サイズの配慮、色のコントラスト、フォームの分かりやすさなども重要です。
読みやすさ・押しやすさ・迷わなさを重視しましょう。
弁護士ホームページの制作費用相場
ホームページ制作をプロに依頼する場合の費用は、制作するページ数によって大きく変動します。
ここでは、制作ページ数別にホームページ制作費用の相場を詳しく見ていきましょう。
制作規模別(シングル〜大規模)の費用目安
シングルページ(5万円~10万円程度)
シングルページの制作を依頼した場合の費用は、5万円〜10万円が目安です。
スマートフォンでも支障なく閲覧できるようにしたり、問い合わせフォームを追加したりするとオプション扱いとなり、別途費用を要するケースもあります。
また、オリジナルのデザインを一からつくるのか、構成から依頼したいのかなどによっても、依頼費用は大きく変わることを覚えておきましょう。
小規模サイト(約10ページ)|30万円~50万円程度
10ページ程度の小規模サイトであれば、30万円〜50万円程度の費用負担で制作できます。
詳細な情報を全て掲載するのは難しいですが、名刺代わりに使用する程度であれば小規模サイトでも支障はないでしょう。
業者が既存のデザインを活用したセミオーダー方式での受注に対応している場合は、費用負担をさらに抑えられることもあります。
中規模サイト(約30ページ)|50万円~200万円程度
30ページ程度の中規模サイトを制作する場合は、50万円~200万円程度の費用がかかります。
事務所概要や各弁護士の紹介、取扱業務、料金表など多くの情報を掲載したい場合は、30ページ程度の規模が必要になることもあるでしょう。
中規模サイトになると、あとで更新作業をしやすくする「CMS」と呼ばれるシステムを導入するかで価格が大きく変わります。
そのため、ホームページを制作したあとの運用方針もあらかじめ検討しておかなければなりません。
大規模サイト(約60ページ)|200万円以上
大規模サイトの制作をプロに依頼した際の費用は、200万円以上を目安にしておきましょう。
大規模サイトでは大量の情報を掲載できるほか、デザインの自由度が高くなるため、独自性を追求しやすい点がメリットといえます。
大規模サイトを制作するうえで、法律事務所のイメージを決めるブランディングにも力を入れたい場合、デザイナーやコンサルタントの力を借りた方がよいこともあるでしょう。
その場合、ホームページ制作費用のほかにデザイン費用やコンサルティング費用も必要になります。
また、大規模サイトになると管理・保守は外部に依頼するケースが一般的なので、制作後に発生する運用コストも考慮しておかなければなりません。
維持費・サーバー・ドメイン代の相場
ホームページは制作して終わりではありません。公開後も継続的に以下の維持費用がかかります。
保守・更新費用:月額5,000円〜30,000円
サイトの安全性維持、コンテンツ更新、技術的なメンテナンス費用です。
基本的な保守のみであれば月額5,000-10,000円、定期的なコンテンツ更新や機能追加を含む場合は月額15,000-30,000円程度が相場です。
WordPressなどのCMSを使用している場合、セキュリティアップデートの対応も含まれます。
サーバー費用:月額1,000円〜10,000円
ホームページのデータを保管・配信するサーバーの月額利用料です。
小規模サイトであれば共用サーバーで月額1,000-3,000円程度、中規模以上のサイトでは専用サーバーやクラウドサーバーで月額5,000-10,000円程度が相場となります。
SSL証明書の費用も含まれることが一般的です。
ドメイン費用:年額1,000円〜3,000円
「○○law-office.com」などの独自ドメインの年間使用料です。
.comや.jpなどの一般的なドメインは年額1,000-2,000円程度ですが、.co.jpなどの法人向けドメインは年額3,000円程度となります。
信頼性とブランディングの観点から、独自ドメインの取得は必須です。
ランディングページ・広告運用費との違い
ホームページ制作費用とは別に、特定の目的のためにかかる費用として「ランディングページ(LP)」の制作費や「広告運用費」があります。
ランディングページ(LP)制作費
特定のサービスやキャンペーンに特化し、訪問者の行動(問い合わせ、資料請求など)を促すことに特化した単一のページです。
一般的なホームページとは異なり、集客のための「入り口」として使用されることが多く、制作費用は数万円から数十万円程度が目安です。
広告運用費
Google広告やSNS広告など、有料広告を出稿する際に発生する費用です。
広告費用は予算に応じて柔軟に設定できますが、効果的な運用には専門知識が必要なため、広告代理店に運用を依頼する場合は別途手数料がかかります。
制作を依頼する場合と自作する場合の比較
ホームページは弁護士自身で作成する方法のほか、プロに作成を依頼する方法もあります。
ここでは、それぞれのメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。
自作のメリット・デメリット
自作のメリットは、自分好みのホームページを納得のいくまで作り上げることができることです。
一から取り組むとなるとある程度の時間はかかりますが、ホームページ作成ツールを利用すれば、素人でも無理なく作業を進められるはずです。
また、プロに依頼するよりコストを抑えられる点も大きなメリットといえるでしょう。
デメリットは、凝ったデザインなどを取り入れたい場合には、HTMLやCSSといったプログラミング言語の習得が必要なことです。
ライティングスキルや、ホームページを検索エンジンの上位に表示させるためのSEO対策スキルなどもある程度必要になります。
制作会社へ依頼するメリット
制作会社に依頼するメリットは、短期間で目的に叶うホームページを作れることです。
素人が自力で制作しようとするとクオリティに限界がありますが、プロなら依頼者の希望を正確に再現することが可能です。
依頼先によってはSEO対策や集客、ブランディングなどのアドバイスを受けられるケースもあります。
また、プロの制作会社は、堅牢なサーバー選定や常時SSL化、定期的な脆弱性診断など、専門家でなければ難しい高度なセキュリティ対策を標準で提供してくれます。
デメリットは、プロにホームページの制作を依頼すると、自分自身で作成するのに比べ費用がかかってしまうことです。
依頼内容にもよりますが、複数ページを制作する場合は数十万円の費用はかかるものと考えておきましょう。
また、大規模なホームページを制作すると、メンテナンスや更新作業を自身でおこなえなくなる可能性もあります。
【参考】大阪のホームページ制作会社 株式会社LIVALEST
依頼時の注意点と見積もり比較のコツ
制作会社選びでは、単純な価格比較だけでなく、提供されるサービス内容を詳細に比較することが重要です。
見積もりには制作費、月額保守費用、オプション料金が含まれるため、総額での比較を行いましょう。
特に弁護士業界での制作実績があるかどうかは重要な判断基準です。
法律用語や業界特有のニーズを理解している制作会社の方が、より効果的なサイトを制作できます。
見積もり比較のポイント
- 制作実績:弁護士サイトの制作経験と事例
- 費用内訳:初期費用と月額費用の詳細
- サポート範囲:制作後の保守・更新対応
また、制作途中での仕様変更や追加機能の料金体系も事前に確認しておくことで、予算超過を防げます。
契約前にはサンプルサイトの確認や、担当者との詳細な打ち合わせを必ず実施しましょう。
ホームページ制作に使える補助金・助成金
弁護士のホームページ制作には費用がかかりますが、国や地方自治体が提供する補助金や助成金を活用することで、その負担を軽減できる可能性があります。
補助金の種類
- IT導入補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 地方自治体のホームページ作成費用補助金
これらの制度は、中小企業や小規模事業者のIT導入、販路開拓、生産性向上などを支援することを目的としています。
IT導入補助金の概要と申請方法
IT導入補助金は中小企業のIT導入を支援する国の制度で、ホームページ制作も対象となります。
2025年度は最大450万円の補助が受けられ、補助率は通常枠で1/2以内となっています。
対象となる事業者
- 法律事務所(従業員数5名以下)
- 資本金または出資総額が5,000万円以下
- 常勤従業員数が100名以下
申請の流れ
- IT導入支援事業者の選定
- 申請書類の準備と提出
- 交付決定後に制作開始
- 完成後の実績報告
申請には事前準備が重要で、「gBizIDプライム」の取得や必要書類の準備に1-2ヶ月程度を要します。
申請期間は年に数回設定されるため、公式サイトで最新情報を確認しましょう。
小規模事業者持続化補助金の対象条件
小規模事業者持続化補助金は、経営計画に基づいて行う販路開拓の取り組みを支援する制度です。
ホームページ制作は「広報費」として申請でき、最大200万円の補助を受けられます。
対象事業者の条件
- 常勤従業員数5名以下の法律事務所
- 商工会議所管内に事業所を有する
- 反社会勢力との関係がない
補助対象となる経費
- ホームページ制作・改良費用
- SEO対策費用
- ネット広告費用
- システム開発費用
申請には経営計画書の作成が必要で、「販路開拓への具体的な取り組み」を明確に示す必要があります。商工会議所での事前相談を活用することで、採択率の向上が期待できます。
【参考】中小企業庁
地方自治体のホームページ補助金一覧
多くの地方自治体が独自のIT支援制度やホームページ制作補助金を設けています。
国の制度と併用できる場合もあるため、事業所所在地の制度を確認しましょう。
主要自治体の制度例
東京都江戸川区
- 販路拡大支援事業助成金
補助額:最大20万円(補助率1/2以内)
対象:外注により、ホームページを作成・リニューアルする際の経費
【参考】江戸川区 デジタル技術活用促進助成事業(IT導入)
東京都港区
- 創業・スタートアップ支援事業補助金
補助額:最大30万円(補助率2/3以内)
対象:新たにホームページを作成する費用
詳細:港区立産業復興センター
福岡県
- 福岡県中小企業IT導入・賃上げ緊急支援補助金
補助内容:国のIT導入補助金の補助率を嵩上げし、事業者負担をさらに軽減
対象:国のIT導入補助金2025(通常枠)に採択された県内中小企業者・小規模事業者
詳細:福岡県中小企業IT導入・賃上げ緊急支援補助金
【制作費用を徹底比較】弁護士・法律事務所向けホームページ制作会社10社
本項では弁護士・法律事務所向けのホームページ制作が得意な以下10の制作会社を紹介します。
それぞれに異なる特徴があるので、予算や制作目的に合わせて適切に選択しましょう。
1. 株式会社アシロ

株式会社アシロは、法律分野に特化した複数のメディアやサービスを展開しており、弁護士業界への深い知見を持つ制作会社です。
法律領域におけるWebマーケティングのノウハウが豊富で、集客に強いホームページ制作を得意としています。
弁護士業界の特性を理解した上で、戦略的なサイト構築が期待できます。
弁護士向けの集客支援サービス「ベンナビ」を運営しており、ホームページ制作と合わせてポータルサイトからの集客も視野に入れた総合的なサポートが可能です。
| 設立年 | 2009年11月 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 西新宿三井ビルディング4F |
| 問い合せ先 | 03-6279-0820 |
| 営業時間 | 平日10時00分~17時00分 |
| 価格 | ライトプラン:10万円 スタンダードプラン:30万円 プレミアムプラン:50万円 |
| 納期目安 | ライトプラン:最短2週間 スタンダードプラン:最短4週間 プレミアムプラン:最短7週間 |
2. 弁護士ドットコム株式会社

弁護士ドットコムは法律相談を専門としたポータルサイトですが、弁護士・法律事務所向けのホームページ制作もおこなっています。
経験豊富な担当者が取材・執筆・制作まで一貫して担うため、認識のずれが起きにくく、要望どおりのホームページが手に入ります。
申込み後最短1ヵ月半で公開できるケースもあり、制作スピードの速さも特徴のひとつです。
また、公開後の更新作業をはじめとしたアフターフォローも非常に充実しています。
文章の修正や画像の入れ替えなど、細かな変更にも柔軟に対応してもらうことが可能です。
| 設立年 | 2005年7月 |
| 所在地 | 東京都港区六本木4-1-4 黒崎ビル |
| 問い合せ先 | 0120-185-006(営業時間 平日10時00分~17時00分) |
| 営業時間 | 平日10時00分~17時00分 |
| 価格 | スタートアップパック:264,000円(税込)〜 集客強化パック:528,000円(税込)〜 |
| 納期目安 | 約1か月半 |
| 公式サイト | https://hp.bengo4.com/ |
3. 株式会社エムハンド

株式会社エムハンドは士業専門のホームページ制作やマーケティング、印刷物まで幅広く手がけるWeb制作会社です。
エムハンドに依頼すれば、細かなコンサルティングを受けながら、ホームページを一から構想できます。
法律事務所としての格式を演出するのか、アットホームでなじみやすいイメージにするのか、どのようなページ構成にするのかなどブランディングへのこだわりも徹底しています。
ホームページ公開後もWeb解析・検証を実施し、Webマーケティングの観点から、さらなる顧客の獲得に向けた改善を進めることが可能です。
| 設立年 | 2003年10月 |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-20-4 Sreed EBISU6F(東京オフィス) |
| 問い合せ先 | 0120-931-574 |
| 営業時間 | 平日10時00分~19時00分 |
| 価格 | 制作例① コーポレートサイト(10P):1,325,500円(税込)〜 制作例② リクルートサイト(12P):1,467,400円(税込)〜 |
| 納期目安 | 制作例① 約3か月 制作例② 約4か月 |
| 公式サイト | https://mh-sp.com/ |
4. アップラボ(サムライラボ)

株式会社アップラボは、士業を対象としたホームページ制作サービス「サムライラボ」を運営するWeb制作会社です。
年間200件以上の豊富な受任実績があるため、はじめてホームページ制作に取り組む場合でも安心して作業を任せられます。
アップラボは、単に情報を掲載するだけではなく、集客・マーケティングを重視したホームページ制作を得意としている点も特徴的です。
特に競合の調査・リサーチには力を入れているため、他社ホームページとの差別化も期待できます。
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区成願寺1-6 アストロタワー27F |
| 問い合せ先 | 0120-959-758 |
| 営業時間 | 平日10時00分~19時00分 |
| 価格 | ゴールドプラン(8〜12P):20万〜40万円 プラチナ(約20P):50万〜80万円 集客強化プラン:80万円〜(個別見積) |
| 納期目安 | 見積書に記載または混雑状況にあわせて個別に回答 |
| 公式サイト | https://www.samurai-lab.jp/ |
5. エファタ(LEAGO)

エファタ株式会社が手がけるLEAGOは、士業専門ホームページ制作サービスです。
単にホームページを制作するだけでなく、集客に必要なSEO対策も含めて対応してくれる点が大きな特徴といえます。
日本全国の弁護士ポータルサイトを運営してきた経験・ノウハウをもとに、「制作後、集客できるサイト」になるまで徹底したサポートを得られます。
また、充実した保守運用体制もLEAGOの強みです。
実績豊富なWebマーケティング会社ならではの視点で、ホームページのメンテナンスや運用改善を図ります。
| 設立年 | 2007年5月 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4-40-12 日興高田馬場ビル8階 |
| 営業時間 | 平日10時00分~19時00分 |
| 価格 | ライトプラン:5.5万円(税込) 独立応援プラン:11万円(税込) 集客重視プラン:33万円(税込) ブランド確立プラン:応相談 |
| 納期目安 | ライトプラン・独立応援プラン:2週間 集客重視プラン:1か月 ブランド確立プラン:2〜3か月。 |
| 公式サイト | https://effata-leago.jp |
6. 株式会社ミリオンバリュー

株式会社ミリオンバリューは、士業に特化したWebマーケティングとホームページ制作サービスを提供しています。
SEOに強く、特定のキーワードでの検索上位表示実績が豊富です。
法律事務所の専門分野に合わせたキーワード戦略に基づき、質の高いコンテンツ制作とサイト構造を提案します。
集客目標を明確にし、成果にコミットする姿勢で、継続的なアクセス増加と問い合わせ数向上を目指します。
| 設立年 | 2010年 |
| 所在地 | 千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 ショップ&オフィス棟6階 KOIL |
| 営業時間 | 平日10時00分~19時00分 |
| 価格 | 初期費用:21万7800円(税込) 月額費用:1万890円(税込) |
| 納期目安 | 約1ヶ月 |
| 公式サイト | https://sigyou-school.biz/ |
7. 合同会社レップリーガル
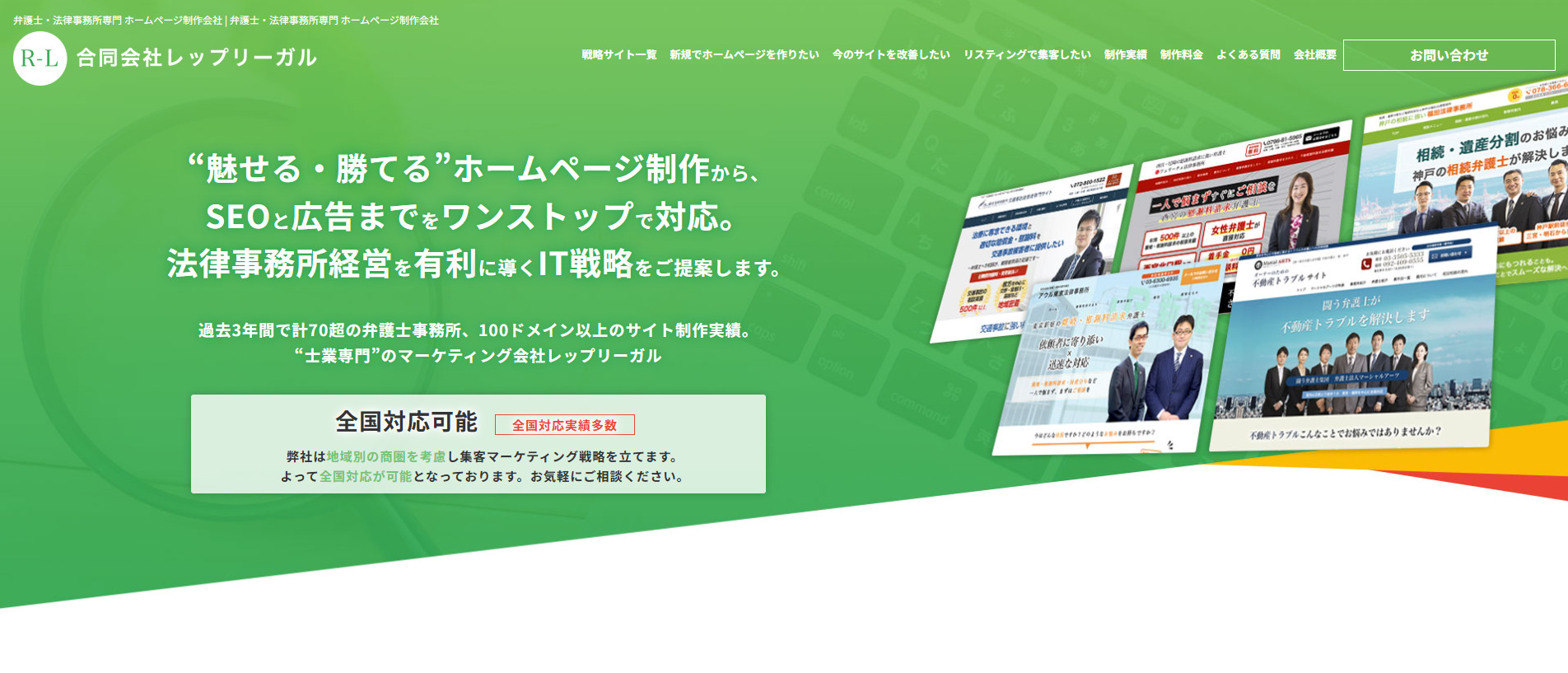
合同会社レップリーガルは、士業専門のWebマーケティングとシステム開発を強みとする会社です。
ホームページ制作だけでなく、集客のためのシステム構築や業務効率化ツール導入など、ITを活用した総合的な支援が可能です。
法律事務所の業務フローを理解した上で、Webサイトと連携した相談管理システムや顧客管理システムなども提案できるため、事務所全体のDX化も視野に入れることができます。
| 設立年 | 2015年 |
| 所在地 | 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8F |
| 営業時間 | 平日10時00分~19時00分 |
| 価格 | フルパッケージプラン:132万円(税込) スタンダードプラン:55万円(税込み) 事務所サイト制作プラン:33万円(税込み) *月間保守管理費用:1万1,000円/月 |
| 納期目安 | 約3か月 |
| 公式サイト | https://replegal.net/ |
8. オフィスSASAJIMA

オフィスSASAJIMAは、地域密着型の士業向けホームページ制作に強みを持つ制作会社です。
特にローカルSEO(MEO)対策に力を入れており、「地域名+弁護士」などの検索で上位表示を狙いたい事務所におすすめです。
親身なヒアリングを通じて、事務所の個性や地域性を活かしたデザインとコンテンツを提案します。
きめ細やかなサポートで、ITに不慣れな弁護士でも安心して制作を進められます。
| 設立年 | 2014年3月 |
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木1-37-26 渋谷YSビル3F |
| 営業時間 | 平日10時00分~19時00分 |
| 価格 | 月額7,800円 |
| 公式サイト | https://office-sasajima.jp/ |
9.ポーカー・フェイス・コンサルティング株式会社

ポーカー・フェイス・コンサルティング株式会社は、弁護士・士業に特化したコンサルティングとWeb制作を一体で提供しています。
制作だけでなく、集客戦略全体をコンサルティングします。
ホームページを単なる情報発信ツールではなく、経営戦略の一部として捉え、具体的な集客目標達成をサポートします。
Web広告運用やSNSマーケティングなど、ホームページと連携した多角的な集客施策を提案し、長期的な視点での事務所の成長を支援します。
| 設立年 | 2013年 |
| 所在地 | 東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 13F |
| 営業時間 | 平日10時00分~19時00分 |
| 価格 | コーポレートサイト制作:624,800円(税込) テーマサイト制作:624,800円(税込) ホームページリニューアル:624,800円(税込) ランディングページ制作:624,800円(税込) 採用サイト制作:1,064,800円(税込) 顧問契約:月額55,000円(税込) |
| 公式サイト | https://www.pokerface.jp/ |
10.株式会社Total Art Development株式会社

株式会社Total Art Developmentは「弁護士WEB」のサービス名で弁護士・法律事務所専門のホームページ制作をおこなっています。
アメリカでの10年以上のWEBマーケティング経験を活かし、弁護士業界特有のマーケティング手法を熟知しているため、各事務所の特性に合わせた適切な集客戦略を提案できます。
また、独立開業を予定している弁護士向けには、ホームページ制作だけでなくOA機器の手配やパソコンのセットアップまで対応する「独立開業支援プラン」も用意されており、事務所立ち上げ時の強力なサポートとなります。
料金体系も明確で、初めてホームページ制作を依頼する方でも安心して相談できる設定となっています。
| 所在地 | 東京都千代田区麹町2-14-6 麹町パレス801 |
| 問い合せ先 | 03-6265-4666 |
| 営業時間 | 平日10時00分~19時00分 |
| 価格 | サイト制作費 217,800円(税込) 月額マネジメント費 107,800円(税込) ※大規模サイトは別見積 |
| 制作実績 | 刑事事件のみを取り扱うアトム東京法律事務所オフィシャルサイト 遺産相続でおなじみの情報ポータルサイト・遺産相続法律相談ナビ |
| 公式サイト | https://www.pokerface.jp/ |
【制作事例】株式会社アシロが手掛けた、弁護士・法律事務所ホームページ
ここでは、実際にアシロが作成した事務所様のホームページ制作事例をご紹介します。
作成時のポイントなどをまとめておりますので、具体的なイメージの参考にしてください。
おおばやし法律事務所
制作の目的・課題
おおばやし法律事務所様は、公式HP開設による信用度の向上と、氏名検索対策を主目的として制作のご依頼をいただきました。
また、仙台エリアでは希少な「英語対応」という強みを訴求し、日本語・英語で切り替えられるHPにしたいとご希望をいただいておりました。
制作でこだわった点・ポイント
仙台エリアのニーズに応えつつ、日本語・英語の2言語切り替え機能を実装し、地域でも数少ない「英語対応可能な法律事務所」としての強みを最大限に可視化しました。
法律事務所の信頼感を伝えるシックでシンプルなデザインと、ご希望いただいた「薄い青・緑」をベースカラーに、派手さを抑えた清潔感のある配色で統一しました。余計な装飾を削ぎ落としたシンプルなデザインは、初めて訪れる相談者に安心感を与え、事務所の信用度を向上できると考えています。
また、先生より提供いただいたトップの背景や、プロフィールお写真と、サイトカラーの雰囲気がマッチしており、余白を活かした読みやすいレイアウトを徹底することで、全体的にすっきりしてみやすいサイトに仕上げることができました。
よくある質問(FAQ)
弁護士のホームページ制作に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。制作を検討する際の参考にしてください。
制作期間はどれくらい?
ホームページの制作期間は、サイトの規模や機能、制作会社との連携のスムーズさによって大きく異なります。
- シングルページ: 簡易的なものであれば、最短1ヶ月半〜2ヶ月程度で公開可能なケースもあります。
- 小規模サイト(約10ページ): 2ヶ月〜3ヶ月程度が目安となることが多いです。
- 中規模サイト(約30ページ以上): 3ヶ月〜半年以上かかることも珍しくありません。
- 大規模サイト(約60ページ以上): 企画からコンテンツ制作、システム開発まで含めると、半年から1年以上を要する場合もあります。
制作会社との打ち合わせの頻度や、原稿・素材の準備状況によっても期間は変動しますので、具体的なスケジュールは制作会社との相談時に確認しましょう。
どんなコンテンツを載せればいい?
弁護士のホームページに掲載すべきコンテンツは、
- 相談者が求める情報
- 事務所の信頼性・専門性を伝える情報
の2つを揃えることが基本です。
最低限、以下は必須項目と考えて良いでしょう。
- 事務所概要とアクセス情報
- 弁護士紹介
- 取扱業務と料金表
- 実績・解決事例
- お問い合わせ・予約フォーム
これらに加え、代表弁護士の挨拶や事務所のポリシー、FAQ、コラムを整備すると、安心感が増して問い合わせにつながりやすくなります。
運用や更新は誰がする?
ホームページの運用・更新体制は、制作方法や契約内容によって異なります。
自作の場合
コンテンツの追加、情報の修正、セキュリティ対策など、すべての運用・更新作業を弁護士自身で行うことになります。
コストは抑えられますが、時間と労力がかかります。
制作会社に依頼した場合
・制作会社に任せる
多くの場合、公開後の保守・運用サービスを提供している制作会社に、定期的なシステム更新、セキュリティ対策、軽微なコンテンツ修正などを依頼できます。
費用はかかりますが、弁護士の負担は大幅に軽減されます。
・CMSを導入し、弁護士が更新
WordPressなどのCMS(コンテンツ管理システム)を導入した場合、制作会社が初期設定やデザインを行い、その後のブログ記事の追加や簡単な情報修正などは弁護士自身で行うことが可能です。
専門知識がなくても更新できるため、コストを抑えつつ鮮度を保てます。
まとめ|成果の出る弁護士ホームページを作るには
弁護士のホームページは、単なる情報提供の場ではなく、集客やブランディング、そして事務所の成長を支える強力なツールとなります。
成果を出すためには、制作段階から公開後の運用まで、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
SEO・UX・ブランディングの3軸が重要
成功するホームページには3つの核となる要素が不可欠です。
SEO対策で継続的な集客を実現し、UX最適化で訪問者を顧客に転換し、ブランディングで競合との差別化を図りましょう。
特に弁護士業界では、地域名を含むキーワード戦略、スマートフォン対応、そして事務所の専門性と信頼性のアピールが重要になります。
料金の透明性や解決事例の豊富な掲載により、相談者の不安を解消することも欠かせません。
制作後の継続的な運用体制もカギ
ホームページは制作して終わりではありません。
月2-4回程度のコンテンツ更新、アクセス解析に基づく改善、セキュリティ対策などの継続的な運用により、真の効果を発揮します。
投資に見合った成果を得るために、明確な目的設定、適切な制作パートナーの選択、そして長期的な運用体制の構築を心がけましょう。